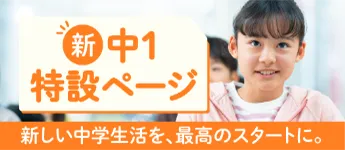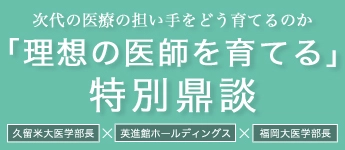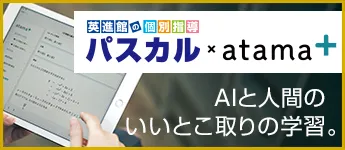荘子
過去の生徒の答案で、「荘子は…に会ったと述べた」という文を英訳して、Shoko said that she had met...と書いているものがありました。
さて、この英文には誤りがあります。どこをどう直すのが正解でしょうか。
どうやらこの生徒は、「荘子」を「しょうこ」さんという日本人女性だと考えてしまったようです。ほかの答案では「そうこ」さんもいました。
しかし、残念ながら、この問題での「荘子」は「そうし」でした。
この問題では、本文の全体的な内容や雰囲気から考えて、中国の故事を述べている文章だと掴むことが必要だったのです。日本人女性のエピソードだと誤解してしまうと、点数が吹っ飛んでしまったでしょう。
荘子は中国の戦国時代の思想家です。道教思想を代表する人物の1人として、世界史や漢文でも登場します。
ただ、別に私はここで、「今の高校生は教養が...」などということを言いたいわけではありません。問題なのは、「荘子」を英語でどう訳すかです。
Shokoと訳すのは問題外ですが、だからといって、SoshiやSoushiというように訳すのが正しいというわけでもありません。
中国語の人名を英訳する時は
中国語の人名を英語に訳す場合、「日本語で読んでローマ字表記にする」というのはNGです。
正しくは、「荘子」は英語ではChuang-tzuです。ShokoでもSoshiでもありません。
ほかに例を挙げておきましょう。
- 孔子:Confucious
- 老子:Lao-tsu
- 墨子:Mo Ti
- 荀子:Hsun-tzu
- 朱子:Chu Hsi
- 始皇帝:Shi Huangdi
- 毛沢東:Mao Zedong
- 周恩来:Zhou Enlai
- 曹操:Ts'ao Ts'ao
- 劉備:Liu Pei
- 孫権:Sun Chuan
ただし、英語で複数の表記法がある人名もあります。
大学入試でこうした単語を書かなければならないというケースはまずない思います。
今回の問題も、実際は、「私は…に会ったと述べた」と考えて、単にI said that I had met...と書けばよい問題でした。
ともあれ、「中国の人名は英語ではローマ字読みではない」ということは押さえておきましょう。