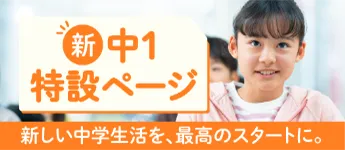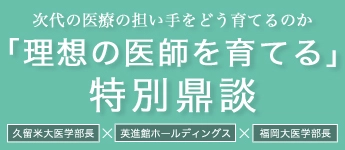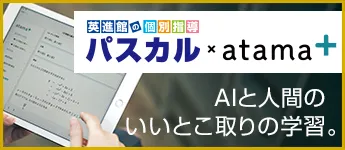sense
senseは非常に重要な多義語です。「(五感のそれぞれの)感覚」、「センス、判断力」、「意味」、「価値、意義」など、さまざまな意味・用法を押さえなければいけません。
in a sense「ある意味では」、in the sense that...「…という意味では」というように、inとセットだと、senseはふつう「意味」です。
lose one's senses「平常心を失う」、come to one's senses「正気を取り戻す」、out of one's senses「気がふれて」というように、one's sensesという形では、「正気、分別」といった意味です。
また、senseは動詞だと、「…を(五感で)感じる、気づく」という意味になります。
もちろん、make sense「意味をなす、筋が通る」、these is no sense (in) ...ing「…しても意味がない」といった熟語も大切。
ともあれ、こうした多義語は、一度でマスターできるようなものではありません。何度も辞書の用例に触れて、一歩ずつ身につけていきましょう。
なお、senseについては、*senceという綴りのミスが散見されます。そう書いてしまう気持ちは分かるのですが、正しくはsenseです。
こうした紛らわしい事項については、「こう考えれば区別できる」という発想を身につけておくのが有効です。
たとえば、senseの綴りについては、次のような派生語と合わせて考えれば、「-ceではなく-seだ」と判断できるでしょう。
- sensitive「敏感な;感覚が鋭い;取り扱いに慎重を要する」
- sensible「分別のある;賢明な」
- sensory「感覚に関する、知覚の」
- sensation「感覚;センセーション、大騒ぎ」
enseのさまざまな意味や綴りは、東大過去問でも出題されています。「こうした重要な単語は、意味・用法・綴りに注意してきちんと身につけておきましょうね」という、大学から受験生へのメッセージだと考えるのがよいでしょう。