高等部 合格者の声
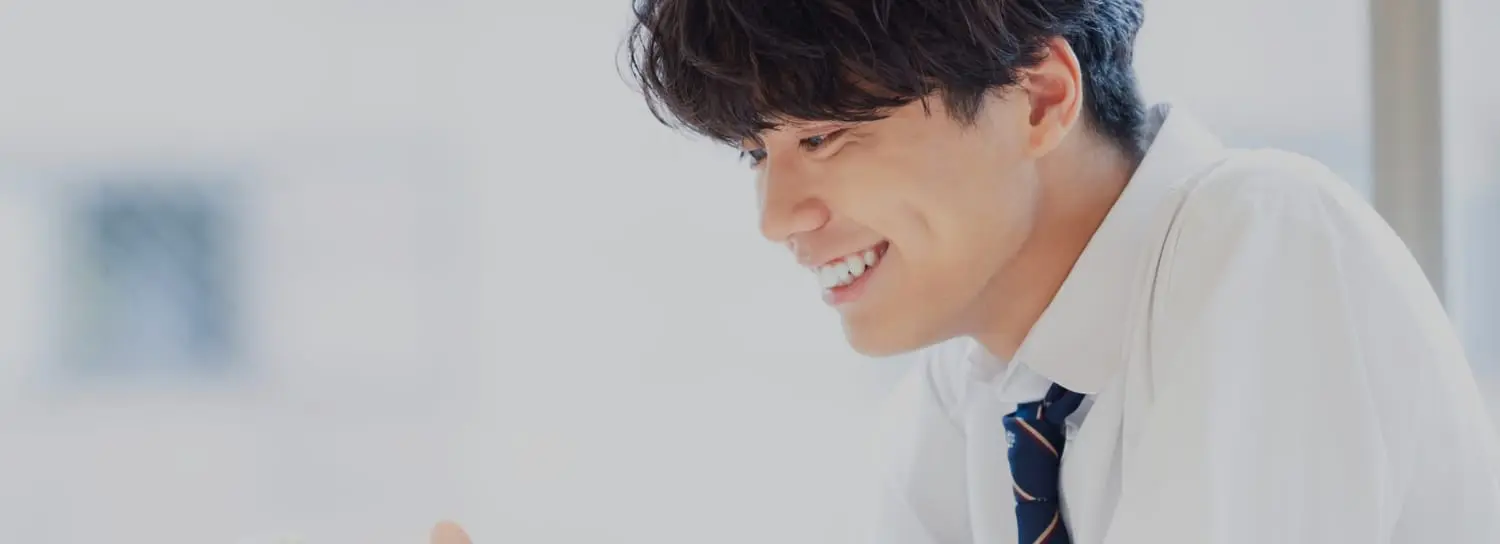
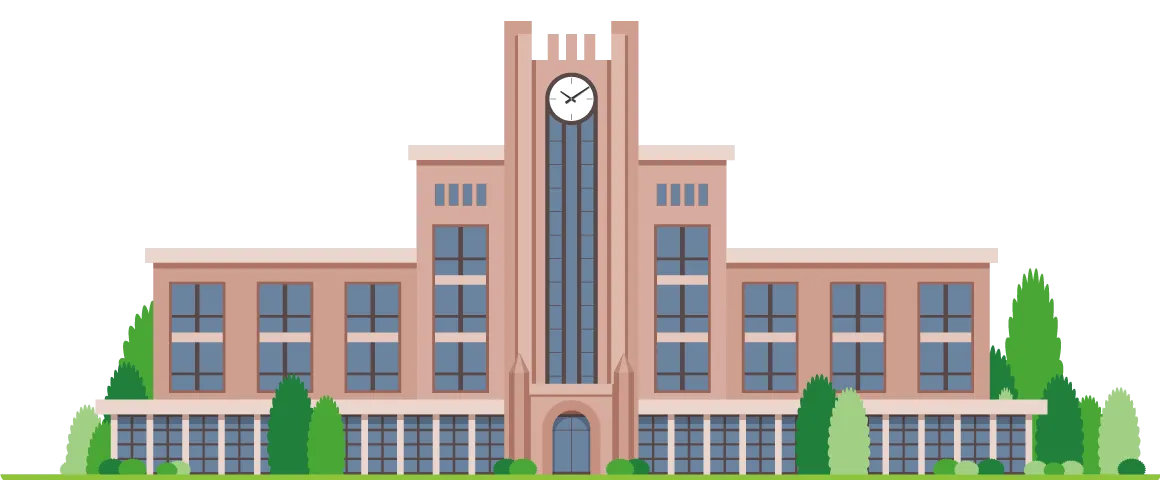
2025年度 東京大学推薦入試合格者対談
2025年3月13日 於天神本館2号館501教室
東大推薦合格者の軌跡
石と小説、異なる情熱が導いた成功
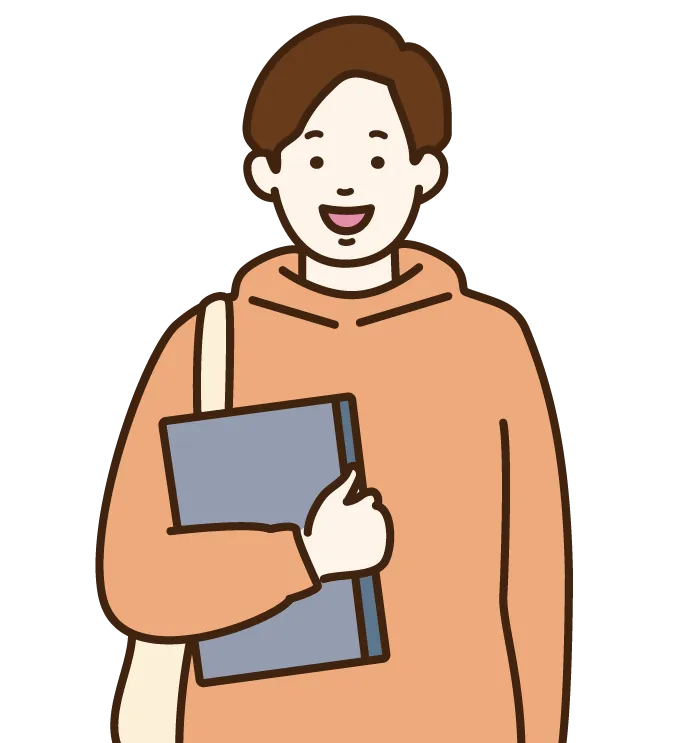
A さん
東京大学理学部合格
(英進館高等部出身)
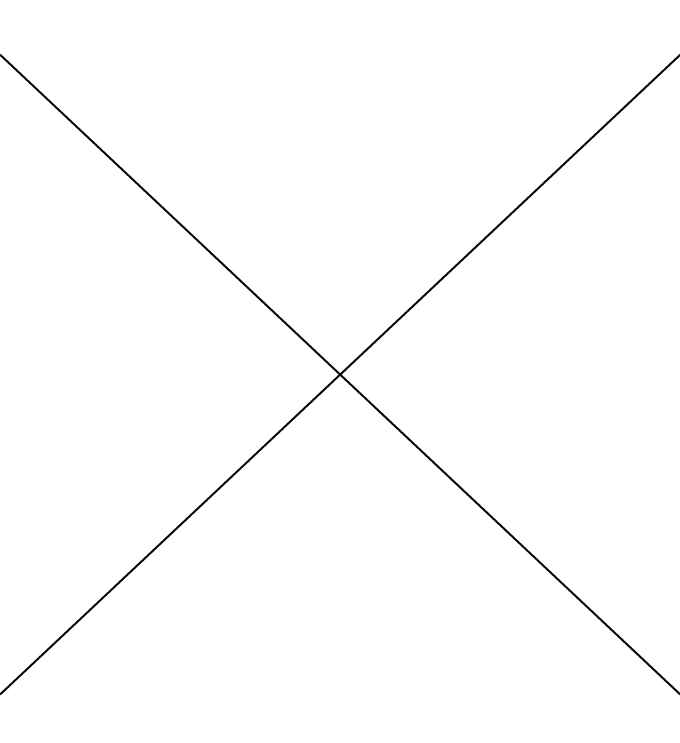

B さん
東京大学文学部合格
(英進館高等部出身)
2025年度東京大学推薦入試(合格者87名)においては、福岡市内在住の英進館生2名が、見事栄冠を勝ち取りました。今回は、お二人に、東京大学の推薦入試にまつわる様々な事柄を、存分に語っていただきました。
司会:竹内 俊介
(天神本館高等部 国語・小論文・地歴公民科)
本日は、わざわざ対談のために来ていただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
挑戦のきっかけ
まず、お二人の挑戦のきっかけから、語っていただけますか。
直接のきっかけは、3年生の夏休みに、学校の担任の先生から薦められたことです。私は昔から石が好きだったのですが、地学、特に地磁気などに興味を深め、部活(化学部)の活動、化学グランプリへの出場などしていたことも背景にあります。
私は、高2のときに、小説の賞をとったことから、意識しはじめました。加えて、自分の学校の先輩が、同じ(東大)文学部に推薦で合格したことにも、刺激を受けました。自分もやってみたら面白いのではないか、と。
どういう小説なんですか?
私は元々中国の文化に興味があって、中国の文化を題材にした小説を書いていました。直近で書いたのは、清の時代を舞台にしたミステリーです。地磁気(への興味)について教えてもらっていいですか?
地磁気については、数十万年に1回反転すると言われていて、もうすぐそれが起こるかもしれません。なぜ反転するのか、反転すると何が起こるのか、探究してみたいという興味です。
やっておいてよかったこと
お二人とも、バックグラウンドというか、東大の推薦を意識する前から、色々なことをされてたと思うのですが、やっておいてよかったことについて教えて下さい。
興味のあることはどんどんやっておいたほうがよいです。私は、推薦に挑戦する前から、小説の賞に応募し続けていました。落ちる可能性のほうが高いのですが、落ちることを怖がることなくどんどん挑戦していたのはよかったかな、と思います。
同感です。好きなことにどんどんチャレンジするのは大事だと思います。私の場合は、石への興味から、登山をはじめたり。石を求めて九州各地を回ったりしました。とにかく動いて、自分の目で触れてみる。そういった経験があったからこそ、(面接官に)熱意を伝えられたのかな、と思います。
積み重ね、ですよね。推薦対策というより「今までの人生の集大成」というか。
そうそう!
お二人は、なぜ石が好きになったか/なぜ小説を書くのが好きになったか、覚えていますか?
結構覚えています。駐車場できれいな緑の石を拾ったときに、宝石かな?と思い、名前はなんだろう、と。石の名前にそれまで興味はなかったのですが、このことをきっかけに調べるようになりました。
よく覚えているんですね。私は、小5のときの自由活動(何をしてもいい時間)で、いつも物語を書いていて、その積み重ねで、書くこと自体が好きになった、という記憶があります。
小説を書くって、どうやるんですか?書き始めとか。
最初にプロットを作って(出来事などを箇条書きにして)書き始める作家さんが多いと思うのですが、私は作ったことがなくて(笑)、頭の中で組み立てて書き始めている感じですね。最近は長編(15万字くらいが目安。文庫本だと300ページくらい)も増えてきたので、そろそろ(プロットなしでは)厳しくなっていますが…。
挑戦における苦労
お二人は、見事合格されて、ここにいらっしゃるわけですが、すべてが順風満帆というわけではなかったと思います。挑戦の過程で苦労したことなどはありますか。
石が好き、地磁気に興味があるというのは確かだったんですが、それを本当に研究テーマにするのか、できるのか、当初固まっていなかった部分もあって、論文や文献を読み込むことで、それを固めていったというところが、あえていうと、一番苦労したところかな、と思います。
私の場合は、小説という大衆文化を研究するという意味で、教養学部を目指すか、(実際に出願した)文学部か、という迷いがありました。研究の方向性が違ってくるので。
周囲の大人のサポート
お二人が、見事合格された、その陰には、ご家族、教師といった、周囲の大人のサポートもあったと思いますが、そのあたりのエピソードを教えていただけますか。
文学部は、事前に論文を提出しないといけないのですが、その際には、竹内先生、それから、三人の学校の先生に見ていただいて、その中で、自分自身の論文の方向性が固まっていきました。とても良い経験だったと思います。
私も、一次選考の書類を作る中で、自分自身の夢が決まっていくという経験をしました。
そうそう、ありますよね。やってるうちに固まっていく感じ。
だから、受けるだけで価値がある、と思います。
あー!わかるわかる!
私の場合は、学校の担任の先生(高2、高3時の担任)が大きかったです。最初に薦めてくれたのも担任の先生ですし、手伝ってくれたのもその先生です。色々なかたちで助けてくださいました。
ご家族のサポートはどうでしたか?
母に、中国文化、文学に関するアドバイスをもらったり、面接練習につきあってもらったりしました。
私の場合は、精神面のサポートが大きかったです。面接の前日にも、大丈夫、といった感じで、励ましてもらいました。
2次選考でのエピソード
第2次選考での印象的なエピソードなど、ありますか?
あります。待合室で30分くらい待たされて、退屈な思いをしたのですが、そのおかげで、緊張はどんどん薄れていきました。前日や、当日も待ち時間に入るまでは、かなり緊張していたのですが、待ち時間が長かったせいで一気に緊張が消えていきました。
私は、待ち時間にほかの人が読んでいる本を、気になってみてしまいました(ほぼ全員が本を読んでいました)。シェイクスピアを読んでいる人、西洋史の本を読んでいる人、色々いました。
さすが文学部、ですね。お二人とも、当然ながら、面接官にとっては「遠くから来た受験生」ですが、そのあたりに触れられることはありましたか?どんな学校ですか?とか。
そのあたりは全くなかったです。厳格な時間制限があるので、そういう質問をしている余裕がない感じでした。
なぜ合格を勝ち取れたのか
これは、ご自身の口からは言いづらいかもしれませんが、「なぜ自分が合格を勝ち取れたのか」と聞かれたら、どう答えますか?
誰もやったことのないところを狙ってみた、というのはあります。小説で入った人はこれまでにもいると思いますし、中国文化の研究で入った人もいると思うのですが、「小説を書ける中国文化の研究者」というのはいないだろう、と。自分にしかない特徴をアピールしていったのがうまくいったということはあります。
同感です。地学に興味のある人自体、少ないですし、自分が興味があったのが、たまたま「狭いところ」でしたから、それが受かりやすさにつながったかな、というところはあります。
推薦合格者の役割
お二人は、一般入試の合格者とは全く違った過程を経て、東京大学に入学されるわけですが、「推薦入試合格者の役割」について、考えるところはありますか。難しい質問かもしれませんが。
「役割」というと、よくわからないところもありますが、一般入試とは、大学の求めている学生のタイプがかなり違う、というのは感じます。
そうですね、そこは同感です。
入学後、頑張りたいこと
一般入試で合格した方々とは違い、お二人は、すでに学部まで決まっているわけですが、こういうことを頑張っていきたいというビジョンは定まっていますか。
私は、電磁気学と流体力学を中心に、学び、究めていきたいと思っています。そのためには、物理もそうですし、シミュレーションに必要な、プログラミング。これは前から興味があって、学んでいましたが、よりレベルを高めていきたいと思います。
私は、引き続き小説の執筆に勤しむとともに、中国文化の研究に力を入れたいと思っています。そして、自分の専門分野以外の授業も積極的に受けていきたいと思います。
挑戦を考えている、あるいは、考えていない後輩へのメッセージ
東京大学の推薦入試。もう挑戦を考えている人もいるかもしれませんが、「敷居が高い」ということで、自分ごととしては考えられていないという人も多いと思います。そうした後輩たちへのメッセージをお願いします。
自分自身、中学校の頃には、「自分が推薦で東大にいける」などとは思いもよらなかったです。とにかく、自分が好きなことに一生懸命取り組むのがいいと思います。そうすれば、「道が拓けるかもしれない」です。
繰り返しになりますが「挑戦するだけで価値がある」ので、何か、すごく興味のある分野を持っている人なら、絶対に挑戦したほうがいいと思います。そして、推薦に挑戦したからといって、それが(一般入試との関係で)重い負担になるということはないと思います。だから、気軽に挑戦してほしいです!
私は結構負担でした(苦笑)。これは人によるかもしれません。ただ、「挑戦することに価値がある」ということについては、本当に同感です。
文系のほうが、事前の準備の負担が大きいんですかね。
文系というか、文学部は一番、事前にこなすべき課題が多い、というのはありますね。二次選考も、小論文と面接どちらもありますし。ただ、一般入試の準備の息抜き、という部分はありました。
理学部は、「事前にやらなければいけないこと」という意味では少ないですね。ただ、「将来いずれ決めなければならないことを今やっている」という感覚はありました。少なくとも私はそう捉えていました。
お二方、非常に濃密なお話、ありがとうございました。私自身が、とても勉強になりました。